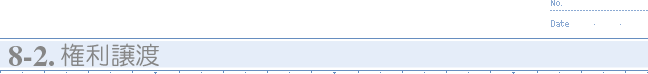
1)序
著作権は財産権であるため、著作権者は、その著作権の全部または一部を他人に譲渡することができます(61条1項)。著作権譲渡は、著作権を譲受けたものがそれを自己の権利として、独占排他的に行使できるというところに特徴があります。
時間的な限定をした譲渡や(東京地判平成9.9.5「ガウディとダリの世界展」事件)、場所的な限定をした譲渡も、契約として認められます。たとえば、半年間の取り決めで複製権の譲渡をしたり、東京での上映に限定して上映権の譲渡をすることもできます。著作権譲渡が行われた場合、著作者と著作権者が分離することになります(3-1.2)参照)。
著作権の譲渡は、著作権者と譲受人とのあいだで行われる契約(準物権契約)です。譲渡契約の原因は売買契約(民法555条)、贈与契約(同法549条)、交換契約(同法586条)などです。たとえば、著作権の売買契約により債権債務が発生し、著作権者は債務の履行として著作権を移転することになります。このとき譲渡契約の原因となっているのが売買契約です。
3段落めはわかりにくいかもしれませんが、著作権者が著作権を売ってお金を手にするのが売買契約、無償でだれかにあげるのが贈与契約、著作権とお金以外の財産権を交換するのが交換契約です。そして、これらの契約によって相手方に著作権を譲渡しなければいけなくなっているということです。著作権譲渡は、著作権の譲渡契約と、その原因となった売買契約などの2本立てとなっています。
2)全部譲渡と一部譲渡
著作権の全部譲渡とは、著作権者が有している権利をすべて譲渡することをいいます。つまり、5-1.に書いている著作財産権すべてを他人に譲るわけです。このとき、たとえばAさんがBさんにすべての著作権を譲渡した場合、Aさんはもはや著作権者ではありません。著作権者はBさんです(Aさんは著作者)。したがって、Bさんだけが著作権を行使することができるのです。
他方、著作権の一部譲渡とは、著作権のうちのいずれかを他人に譲ることをいいます。たとえば複製権だけを譲渡することができ、または複製権に加えて翻案権を譲渡することもできます。著作権は支分権の集まりなので、一部譲渡が可能となるのです(1-3-3.参照)。
3)性質
著作権譲渡契約は準物権契約であり、物権的効力を有しています。準物権契約とは、第三者に対して主張できる権利の移転を目的とした契約のことをいいます。よって、著作権を譲受けた者は、その権利を第三者に対抗することができます。
第三者に対抗できるというのは、すなわち第三者に対して自己の権利を主張できることを意味しています。ただし、取引の安全の観点から登録が対抗要件とされているため、登録している場合に限られます(77条1号)。対抗要件とは、第三者に対して自己の権利を主張するための要件のことをいいます。対抗要件を具備していなければ第三者に対して対抗できません。
たとえば、著作権者であるAさんが、Bさんとのあいだで複製権の譲渡契約を締結して、Aさんは複製権を失い、Bさんは複製権を得たとします。このとき、かりにAさんがCさんに対して同様に複製権を譲渡していた場合(二重譲渡)、Bさんは複製権を登録しておけば、第三者たるCさんに対して侵害の差止請求(112条)や、損害賠償請求(民法709条)ができるのです(10-3.1)で後述)。しかし、複製権を登録しておかなければ、BさんはCさんに対してそのような請求ができません。これが、第三者に対抗できる、できないということの意味です。
なお、いまの例でなぜAさんがBさんとCさんの双方に、二重に権利を譲渡することができるのか、疑問に思った方がいるかもしれません。この点については、民法176条(意思主義)や177条(物権変動の対抗要件)のあたりを概説書で参照してください。また、あくまでもCさんが複製権を登録していないことが前提となっています。先にCさんがBさんよりも早く複製権を登録してしまえば、もはやBさんはCさんに対し、原則として対抗できません。
著作権が物権的効力を有しているということを理解するためには、物権が何なのかということをまず把握しなければいけません。物権といっても、いろいろなものがあるのですが、代表的なものに所有権(民法206条)をあげることができます。かりに、みなさんの自動車がだれかに火をつけられて全焼してしまった場合、所有権を侵害されたことを理由に、加害者に対し損害賠償請求をするでしょう。
ではなぜこのような主張ができるのかというと、あなたが所有権を有している物、すなわち絶対的に支配している所有物を、他人が故意または過失によって侵害しているからなのです。「絶対的」というのは、だれに対しても権利を主張できることを意味しています。つまり、特定人に対してだけではなく、円満な支配を侵害する者すべてに対して、権利を主張できるということです。
これはあたりまえのことだと思うかもしれませんが、債権の場合は相対的な権利であるため、そうはいかないのです。たとえばAさんとBさんが、Aさんが所有する本をBさんに売渡す契約を締結したとします。この場合、AさんはBさんに対して「お金を支払え」と請求でき、BさんはAさんに対して「本を渡せ」と請求できます。特定の人に対してある行為を請求する権利を債権といいます。つまり、AさんもBさんも債権を有しています。このとき、AさんはあくまでもBさんに対してのみ債権を行使できるだけであり、BさんもまたAさんに対してのみ債権を行使できるだけです。よって、第三者である近所のCさんに対して、債権を行使することはできないのです。
このように、物権は絶対性があるがゆえにだれに対しても権利を主張できるのですが、債権は相対的な権利であるがために、特定の人に対してしか権利を主張できません。著作権は、この民法上の概念である物権と類似の性質を有しているため、「準物権」とよばれているのです。「準」が付いているのは、著作権は物権そのものではなく、物権に似たものでしかないからです。
4)翻案権の留保
譲渡契約において、翻案権(27条)または二次的著作物利用権(28条)についての定めがない場合は、譲渡人にこれらの権利が留保されたものと推定されます(61条2項)。本条の趣旨は、一般的に弱い立場にある著作者を保護するためです。
留保というのは権利が移転せずに留まるという意味です。たとえば、AさんがBさんにすべての著作権を譲渡したとします。ところが、当該譲渡契約において、翻案権(二次的著作物利用権)についてはなにも取り決めていませんでした。この場合、翻案権(二次的著作物利用権)だけはBさんに移転しなかったものと推定されるのです。
