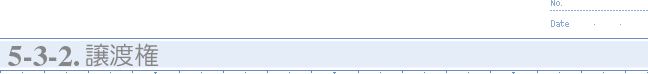
1)定義
譲渡権とは、著作物を原作品またはその複製物の譲渡により公衆に提供する権利です(26条の2第1項)。映画の著作物は頒布権で処理されるため除きます。
ここでいう「複製物」とは、私たちがふだん目にしている音楽CDや本などの商品や、商品をダビングなどにより複製したもののことです。これらはオリジナルである原盤や原稿を複製したものであるので、複製物として扱われています。
また、公衆とは、不特定または多数のことをいいます(2条5項参照)。したがって、少数でも不特定であるなら「公衆」に該当し、特定でも多数なら「公衆」にあたります。逆に、特定かつ少数ならば「公衆」とはいえません。よって、特定かつ少数の者に対する譲渡には譲渡権が及ばないことになります。
ただし、公衆にあたるか否かは、「著作物の種類・性質や利用態様を前提として、著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案して判断するのが相当である」ため、一義的に定めることは難しく、合目的的な判断を要するところです(名古屋地判平成15.2.7「社交ダンス教室」事件)。
お店は不特定の人を対象としているので公衆に該当します。また、特定の会員向けのお店であっても、会員が多数いる場合(目安で50人超)はやはり公衆に該当します。
しかし、特定の会員向けのお店で、なおかつ少数の場合は、特定少数ですので公衆に該当しません。ただし、その場合であっても、入会金さえ払えばだれでも入会できるなど、人を広く募るようなものだと、公衆に該当する可能性が出てきます。けっきょくのところ、公衆に該当するか否かは個別具体的な判断が必要です。
2)趣旨
従来は、映画著作物に限ってその複製物を頒布(譲渡・貸与)する権利が認められているだけであり、映画著作物を除いた一般の複製物については、公衆に貸与する権利が認められているだけで、公衆に譲渡する権利は認められていませんでした。
また、譲渡権を新設することにより、他人が著作物を複製する場合に加え、当該著作物を他人が公衆へ譲渡する場合においても、著作権者は再び対価を取得する機会を与えられることになり、利益を著作権者に還流させることが可能となります(田村・概説153〜154頁)。
そこで、1999(平成11)年改正により、映画著作物を除いた一般の複製物についてについても、公衆に譲渡する権利が認められました。
1999年改正前、すなわち譲渡権が新設される以前は、違法に作成された物についてのみ、情を知ってそれを頒布したり、頒布目的で所持する行為が禁止されているだけでした(113条1項2号)。そのため、著作権者の許諾を得て適法に複製された物を譲渡することは、問題のない行為でした。ところが、譲渡権が新設されたことで、たとえ適法に複製された物であっても、それを公衆に譲渡する場合は著作権者の許諾が別途必要となったのです。
もっとも、出版などの場合には、複製の許諾だけではなく譲渡の許諾もあると考えられるため(黙示の許諾)、譲渡権が新設されたことによる実務上の変化はほとんどないものとされます(中山・著作権法233〜234頁)。
3)権利の行使
(1)譲渡権侵害を主張できるケース
以下の場合は、譲渡権侵害を主張できる典型的なケースです。
- 著作権者Xに無断で、Xの作成した著作物をAが複製してBに譲渡した場合
- 1のケースにおいて、Bがその複製物が違法なものであることを知りつつ、さらにCに譲渡した場合
- 著作権者XがAに対して複製の許諾のみを与えたところ、Aがその複製物をBに譲渡した場合
- 3のケースにおいて、BがAの譲渡は違法であることを知りつつ、さらにCに譲渡した場合
まず、1のケースから説明します。著作権者たるXさんはAさんに対して、譲渡権を侵害されたと主張できます。一番シンプルな例です。
つぎに2のケースですが、これはBさんが違法な複製物であることを知りながらCさんに譲渡してしまった場合です。このとき、XさんはAさんとBさんの双方に対して、譲渡権侵害を主張できます。
そして3のケースですが、Xさんが複製についての許諾を与えたのみであって、譲渡の許諾を与えていないので、Aさんに対して譲渡権侵害を主張できます。
最後に4のケースです。これも2のケースとまったく同じ例です。
では、2および4のケースにおいて、Bさんが違法な複製物であることを知らずにCさんに譲渡した場合はどうなるのかということですが、これについては下記(2)で述べます。
(2)譲渡権侵害を主張できないケース
以下の場合は、譲渡権侵害を主張できません。
- 上記(1)2のケースにおいて、Bが違法な複製物であることを知らず、かつ無過失でそれをCに譲渡した場合(113条の2)
- 上記(1)4のケースにおいて、Bが違法な譲渡であることを知らず、かつ無過失でそれをCに譲渡した場合(同条)
- XがAに複製と譲渡の許諾を与えたところ、Aが当該複製物をBに譲渡し、BがさらにCに譲渡した場合(26条の2第2項1号・3号)
ポイントは「かつ」ということばです。すなわち、Bさんが違法な複製物であることを知らなかった場合でも、知らなかったことにつき過失がある場合は、Xさんは譲渡権侵害を主張できます。他方、Bさんが当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がないときは、Xさんは譲渡権侵害を主張できないのです。
このほか、3のケースにおいても譲渡権の侵害を主張することはできません(譲渡権の消尽)。譲渡権の消尽は重要なので、項目を独立して下記4)で解説します。
4)譲渡権の消尽
以下のいずれかに該当する適法な譲渡による場合は、譲渡権が消尽します(26条の2第2項)。なぜなら、譲渡のたびに著作権者の許諾を求めるとすると、迅速で円滑な取引を阻害してしまいますし、著作権者は許諾を与えた著作物につき、それが転々譲渡されるであろうことを予測していると考えられるからです。
- 譲渡権を有する者、または許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品や複製物(1号)
- 2号(省略)
- 譲渡権を有する者、またはその承諾を得た者により、特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品や複製物(3号)
- 4号(省略)
いったん適法に譲渡されれば、譲渡権は消尽します(ファーストセール・ドクトリン)。たとえば著作権者たるXさんが、自身が作成した著作物にかかる譲渡許諾をAさんに与え、Aさんがその著作物をBさんに譲渡し、BさんがさらにCさんに譲渡したとします。
この場合、Aさん→Bさんの譲渡についてはXさんの許諾があるので適法なのはもちろん、Bさん→Cさんの譲渡についても適法となるのです。なぜなら、Aさん→Bさんの譲渡(第一譲渡)は適法なものであり、そのためBさん→Cさんの譲渡(第二譲渡)につき譲渡権は消尽しているからです。
したがって、私たちがお店で購入した音楽CDを売ったり、あるいは中古店が中古CDを販売するさいには、著作権者の許諾を得る必要はありません。
ここで注意が必要なのは、第一譲渡が適法な場合にのみ譲渡権の消尽が適用されるということです。つまり、第一譲渡が違法な場合には、譲渡権の消尽は適用されません。この点については、上記3)(1)に示した2および4の具体例のとおりです。
5)複製権の制限により作成された複製物の譲渡
譲渡権にいっさいの制限を認めないとすると、他の条文との関係上、不都合が生じる場合があります。たとえば、著作物は一定の場合にかぎり、教科用図書に複製して掲載することができますが(33条、6-3.2)で後述)、複製できても譲渡(販売)できないのであれば、33条の意義が失われてしまいます。そこで、複製権の制限により作成された複製物を譲渡する場合には、譲渡権が制限されます(47条の4)。
ただし、図書館における複製(31条1号、6-3.1)で後述)など、複製の目的につき制限が設けられているものについては、目的外の譲渡がされた場合には譲渡権が及び、譲渡権侵害となります(47条の4但書き)。また、同時に複製権侵害となります(49条、6-7.3)で後述)。
教科用図書を作成して販売する業者は、教材として他人の小説などを複製します。これは違法行為ではないのですが(33条)、かりに譲渡権が制限されないとなると、小説を教材にした教科用図書を譲渡(販売)できないことになってしまいます。これでは教科用図書に他人の著作物を複製できるとする33条の趣旨を没却してしまうので、譲渡権も制限されるということです。
