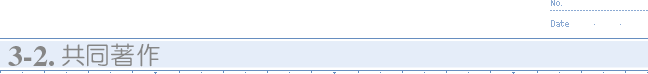
1)共同著作の定義
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを共同著作物といい(2条1項12号)、それらの各著作者を共同著作者といいます。たとえば、だれがどこを担当すると決めずに共同で本を書いた場合、当該本は共同著作物といえます。
かりに、本の第1章をある者が執筆し、第2章を別の者が執筆したというような場合は、各人の創作的な寄与を個別的に利用できるため、共同著作物とはいえません。このように、概観上は1個の著作物のようでありながら、作品全体の創作に関しての共同行為がみられず、それぞれ独立した著作物が結合しているものを結合著作物といいます。
座談会や討論会などは個々の発言が相互に影響しあって完成するものであり、個々の発言には独自の価値がありません。よって、利用可能性がないため、共同著作物になると解されます(半田・概説60頁)。
これに対し歌謡曲は、歌詞と楽曲という、個別に利用可能なものどうしが結合したものであるため、結合著作物といえます。ほかには、ミュージカルやオペラ、挿絵が入った新聞小説などが結合著作物です。
2)要件
共同著作物といえるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 2人以上の者が創作に携わること
- 共同関係があること
- 著作物が単一の形態をなし、各人の寄与を分離して個別的に利用できないこと
(1)共同創作性
通常、共同著作物を作成するさいには、当事者は共同で著作物を作成しようという共通の意思(共同創作の意思、共同意思)を持ち、連携をとっていくものです。しかし、ある研究者の書籍をその死後、別の研究者が改訂した場合など、共同創作の意思や連携関係がなく結果的に複数人が関与した著作物ができたとき、これは共同著作物なのか、それとも二次的著作物なのか判然としません。そこで、共同著作物と二次的著作物とを区別するため、共同創作性の要件が設けられているのです。
では、何をもって共同創作性の要件を満たしているといえるのでしょうか。この点については、主観的な要素を重視すべきでなく、客観的にみて当事者間に、たがいに相手方の意思に反しないという程度の関係が認められるか否かで判断すべきという見解(客観的判断説)がある一方で、主観的な要素を重視し、たがいに相補うかたちで創作するという認識があるか否かによって判断すべき、という見解(共同意思説)が対立しています。
共同意思説は、共同著作物というのは著作者の権利を制約するものであり(64条2項、65条3項参照。ともに下記3)で後述)、そういった制約を正当化しうるためには、共同著作物が成立する範囲をできるだけ限定的にしたほうがよいという理由によるものです(田村・概説370頁〜)。
他方、客観的判断説は、主観的な要素が外部からは識別しにくいことを理由としています(半田・概説57頁)。この見解については、二次的著作物とすることにつき当事者の心情的な問題も影響しているのではないかという指摘があります(作花・詳解183頁)。
それぞれの理論にさきの事例をあてはめると、客観的判断説では共同著作物となり、共同意思説では二次的著作物となります。
(2)分離利用不可能性
分離して利用することができない場合でなければ、共同著作物とはなりません。この分離利用不可能性の要件は、1)で前述した結合著作物と区別するために設けられたものです。
3)効果
(1)共同著作物の著作者人格権
共同著作物は各著作者の人格的利益が融合したものであるため、各著作者が個別に著作者人格権を行使するのは不適切といえます。そこで、共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ行使できないものとされています(64条1項)。
また、著作物の利用が停滞する事態を防止するため、各共同著作者は信義に反して前項の合意の成立を妨げることはできません(同条2項)。
共同著作物の著作者は、そのうちから著作者人格権を代表して行使する者を定めることができますが(同条3項)、代表権を制限している場合、取引の安全のため善意の第三者に対抗することができません(同条4項)。
代表権の制限というのは、たとえば共同著作者であるAさん・Bさん・Cさんらの取り決めで、「Aは著作者人格権を代表して行使できるが、著作者人格権の不行使契約(8-5.1)(2)で後述)は第三者と締結することはできない」ということになっていたとします。
ところが、Aさんはこの取り決めを無視して、事情を知らないDさん(=善意の第三者)と著作者人格権の不行使契約を締結してしまいました。このときBさん・Cさんは、Dさんに対してその契約が無効であることを主張できないということです。もしも契約が無効であることを主張できるとすれば、代表権が制限されていることを知らないDさんに不測の損害を与え、取引の安全を害してしまうからです。
(2)共有著作権の処分・行使
共同著作物の著作権は、各共同著作者の共有となりますが(民法264条・249条、準共有)、著作権の共有関係の特質に鑑み、著作権法にはその特則が規定されています。
まず、共有著作権の各共有者は、その持分を譲渡または質権の目的とするなど、共有著作権を処分するためには、共有者全員の合意を得なければいけません(65条1項)。各共有者にとって、だれがメンバーに加わるかは、自己の利益と関連する重大な関心事項だからです。
また、各共有者が著作物を自由に利用できるとなると、共有者の利益を過度に害することになりかねないので(中山・著作権法193頁)、共有著作権は共有者全員の合意によらなければ行使することができなものとされています(同条2項)。
この65条1項・2項の場合において、各共有者は正当な理由がない限り、同意を拒んだり合意の成立を妨げることはできません(同条3項)。正当な理由が必要なのは、著作物の利用・流通を過度に阻害しないようにするためです。64条2項の「信義に反して」という文言に対して、本項は「正当な理由がない限り」と規定されており、具体的な意味につき争いがあります。
10-3.著作権侵害の効果で後述する差止請求や、損害賠償請求、不当利得返還請求は各共有者が単独でできます(117条)。著作者人格権を侵害された場合にも同様のことが単独でできるかについては、争いがあります。
64条3項・4項の規定は、共有著作権の行使について準用されます(65条4項、上記(1)参照)。
共有とは、ひとつの物を数人で共同所有する形態をいいます。たとえば、車を共有するということは、複数の人間が1台の車を所有していることをさします。準共有というのは、共有するものがこういった所有権ではなくて、所有権以外の財産権(著作権など)である場合をいうのです。
各共有者が目的物に対して有する所有の割合を持分といいます。たとえば、1台の車を3人で共有している場合、それぞれが3分の1の持分を持っていることになります(民法250条)。共同著作物の場合、各共同著作者の持分は各人の寄与度によりますが、寄与度が不明瞭の場合は相等しいものとして持分が決定されます(同条、東京地判平成9.3.31「だれでもできる在宅介護」事件)。
質権というのは、債権者がその債権を担保するために、債務者などから受け取った物を占有して、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことをいいます(民法342条)。大ざっぱにいえば、債務者が財産に質権を設定して一時的にその目的物を債権者に引渡し、債権者からお金を借りるのです。借金を返済できなければ、質権の目的物は競売にかけられます。買い手がいればその人が所有権者となり、代金は債権者が取得します。
著作権の場合も基本的に同じですが、著作権に質権を設定した場合、とくに当事者間で取り決めがない限り、質権者ではなく著作権者が著作権を行使できる点には注意が必要です(66条1項)。また、目的物の引渡しも必要ありません。著作権者がお金を手に入れるために、著作権に質権を設定するのだと理解しておいてください。
不当利得など見慣れない用語が出てきたかもしれませんが、いまは流し読みしておいてください。詳細は10-3.で後述します。
